小説 お女郎縁起 第四章 石川島―寛政2年(1790)2月~寛政3年(1791)8月
小説 お女郎縁起
寛政秘話 石神女郎仏と大宮お女郎地蔵
奮闘
寛政2年2月28日長谷川平蔵は隅田川の河口、石川島にいた。ここは幕府旗本で船手頭の石川大隅守の屋敷があったことから石川島と呼ばれている。平蔵は前年老中松平定信に建議していた無宿人厚生施設建設が認められ、この石川島の南側の中州に施設の建設を始めたのである。これを人足寄場という。
幕府は徳川吉宗の頃から江戸に流入し治安を乱す無宿人対策に頭を悩ませており、度々無宿人の為の施設を作ってみたもののことごとく失敗している。
10年前も深川茂森町で無宿養育所が作られたが、大量の死者と逃亡者が出て頓挫している。老中首座松平定信は天明の飢饉で無宿人が急増して、江戸打ち壊しなどの大騒動が起きたことを問題視して、従来と一線を画す施設の建設するための意見を募った。そこに建議書を出したのが御先手組弓頭および火付け盗賊改め長官の長谷川平蔵だった。今で言えば自衛隊精鋭部隊と警察テロ専門部隊の隊長が犯罪者やホームレスの厚生と更生を兼ねた施設を作るようなものであり、いかに意外かが分かる。しかし、平蔵が懸念した自分の案が取り上げられるのかどうか?というのは杞憂だった。他の武士たちは最初からそんなことは下賤の者がやることだと思っていたので、平蔵以外手を挙げる者がいなかったのである。平蔵が神道徳次郎を捕まえるなどの手柄は全く関係なかったのだ。
平蔵は上機嫌だった。この日彼は念願かなった人足寄場の建設予定地で鍬入れ式を執り行っていた。鍬入れ式の日にもかかわらず、平蔵はさっそく20人ほどの無宿人を集めて訓示をしていた。
「諸君!今日この人足寄場に集められた諸君は、江戸で困窮し、犯罪に手を染め、人々から蔑まれる無宿人達の代表である。この度、お上はこの長谷川にこの対策を一任された。この長谷川は今まで厄介者を閉じ込めるだけのような収容所ではなく、諸君がここで手に職を持ち、貯金をし、性根を直して社会復帰する手伝いをする施設を作る。これが成功するかどうかは、ここに集まった第1期生の諸君にかかっているのだ!」
平蔵は一呼吸入れて皆を見回した。皆紅潮し、感激の面持ちである。平蔵はご満悦である。平蔵が言うようにこの人足寄場は無宿人たちの社会復帰を目指すものである。収容された無宿人達は人足としてここで仕事をし、手に職を付け、自立のすべを得て社会に戻るのである。日本初と言って良い福祉事業なのだ。平蔵は訓示を続けた。
「そもそも犯罪をしたくてやっている者はほとんどいない。犯罪を犯さざるを得ない境遇に置かれることで止む無くやっているのだ。俺も昔は「本所の鐵(てつ)と呼ばれるようなワルだった。だからこそ諸君の気持ちがわかる。若い頃の俺はそりゃあ悪かった。飲む打つ買うの三拍子、喧嘩は日常茶飯事だ。」
演説に興が乗り始めた平蔵を、内藤数馬は冷ややかに見つめていた。
(始まった。お頭の悪い癖だ。話が長くなると段々脱線して、最後は何言っているか分からなくなるんだ。ほら、やくざの出入りに加勢した話に変わっている。こんな話聞かせてどうするんだ。案の定みんなダレてきた。)
ようやく平蔵の長い長い話が終わった。数馬はやっと式が始められると安堵したが、(何か変だぞ?鍬入れ式なのに盛り土がない。神主もいない。)
数馬が不審に思っていると、平蔵が言った。
「これより鍬入れ式を始める。みんな鍬を持ってついて来い。」
平蔵はそう言って一人一人に鍬を持たせた。そして、
「これはおまえのだ。」
と言って数馬にも鍬を持たせると、皆を宿舎建設予定地に連れて行った。そして全員が揃うと、
「今からここの整地作業をする。」
と言った。皆「ええ~!?」と驚いた。
「何してる?ここにおまえらが寝泊まりする小屋を作るんだぞ。早くしないと野宿だぞ。」
そう平蔵が言うと、皆いっせいに土を耕し始めた。
「お、お頭!本当にやるんですか?今?」
数馬は驚愕した。
「当たり前だろう?建設資金が足りないんだ。作業は自分たちでやらねえとな。何してるんだ数馬。早くおまえもやれ。」
平蔵は無駄の無い男だった。
(なんで私まで。)
数馬は嘆いたが、整地と仮小屋はその日のうちに完成した。
人足寄場の建設資金は確かに足りなかった。これも幕府の財政不如意によるものなので平蔵も仕方ないと思っていた。その代わり平蔵は知恵と工夫で建設を進めていった。空き家になった武家屋敷を解体して材木を確保したり、中州を埋め立てして、その空き地を材木商の資材置き場にして地代を取ったりして節約と資金確保に充てていた。他の旗本ならプライドが邪魔をしてこんなことは出来ないが、平蔵にそんなこだわりは無かった。
一月後、内藤数馬は平蔵に石川島に来るように言われた。人足寄場の建築現場に行くと平蔵が人足達にあれこれ指図をしていた。建築は急ピッチで進められ、すでに無宿人達の収容が始まっていた。
「おう!来たか!」
平蔵は上機嫌だった。
「どうだい?立派なもんだろう?」
「はい。凄いですね!ろくに資金も無いのに、こんな立派な施設になるとは。」
数馬は感心した。
「そうだろう?でよ、ちょっとお前に相談があるんだ。」
そう言うと平蔵は埋め立て地の岸に数馬を引っ張っていった。
「これを見ろ。数馬。せっかく埋め立てしたのに川に削られているだろう?」
護岸がされていない埋め立て地の岸は、川の流れにどんどん削られていた。
「そうですね。このままでは築地が崩れてしまいますね。」
「そうなんだ。そこで早急に護岸をしなきゃならねぇ。それでおまえにその役をやってもらいてぇのよ。」
数馬は動揺した。
「ええ!?私が?私は犯罪捜査官ですよ?そんなこと出来ませんよ。」
「だからよ。おまえ一人にはやらせねえから。同心を2,3人付けるからよ。頼むよ。みんな忙しいんだからさ。」
「私だって忙しいのに。でも分かりました。やればいいんですよね?やれば。」
数馬はしぶしぶ引き受けた。
「で、工事はどこの業者ですか?護岸用の石は材木石奉行に掛け合うんですか?」
「・・・・・」平蔵は沈黙している。
「お頭?どうなんですか?」
「工事はここの人足達を使っておまえの指揮で行う。石は浅草寺とかの無縁仏の墓石を持ってくる。」
「ええっ!?」数馬は仰天した。
「じゃあ頼んだぞ!」
そう言って平蔵は現場に戻っていった。
(馬鹿な!無茶苦茶だ!)
捕り物に建築にと忙しい平蔵だが、石川島の埋め立て地の護岸が気になっていた。雨の季節が近づいていたので、それまでに護岸を終わらせたかったのだ。
(数馬の奴、ちゃんとやってるかな?ちょっとはっぱを掛けに行くか?)
墓石調達の様子が気になった平蔵は浅草の船着場まで来た。作業は順調に進んでいて、寺から運んだ石が河岸に積み上げられていた。平蔵は安心したが、何故か指図役の数馬がいない。近くで人足達の作業を見守っている同心に数馬は何処に行ったのか聞くと、後ろに居りますとのこと。振り返ると人足姿の男が真後ろに居た。
「お頭、何しに来たんですかい?」数馬だった。
「お、お前いつから武士辞めたんだ!?」平蔵は驚いた。
「何言っているんですか!辞めていませんよ。こんなところを知り合いに見られたら恥ずかしくて仕方ないでしょ!だから分からないように変装しているんです!」数馬は憮然とした。
「そ、そうか!それは悪かったな。でも変装うまいじゃねえか。本物だと思ったぜ。」
「お頭のせいですよ!まったく!」数馬はぶつぶつ言いながら手際良く指図をしている。
(これは意外だった。数馬にこんな才能があるとは。今度は埋め立て工事をやらせて見よう。)
奇策
寛政3年(1791)4月、1年経った人足寄場の運営は軌道に乗り、収容者も150人を数え、初の退所者も出た。退所者には自分で積み立てた貯金を返し、学んだ職に必要な道具まで与えた。しかし、中には全く更生する気もない者もいて、収容所の風紀を乱したり揉め事を起こしたりしていた。犯罪者のすさんだ心を直すのは難しいのだ。それでも平蔵はあきらめなかった。(心を尽くせ!)
本所牢で杉浦五大夫に言われた言葉が平蔵の支えだった。
もう一つ平蔵を悩ませていたことがある。それは人足寄場の運営資金が削減されたことであった。初年度は約800両だったものが、600両に減らされていた。年々収容者を増やそうと考えていた平蔵にとって頭の痛い問題だった。
(これからって時に。事業は2年目からが大事なのに。これでは現状を維持するのも難しい。)
平蔵は人足寄場の運営資金を減らされた後、老中首座松平定信のもとを訪ねた。用件は物価高により庶民が困窮している。ついては窮民対策として下賜金を賜りたい。ということだった。同時に江戸の商人を集めて物価を下げるよう説諭をするという。窮民に補助金を与えることと、商人に自主的に値下げをさせることで多少は江戸市民の生活が楽になればということで定信は許可し、3千両を平蔵に下賜した。
ある日内藤数馬が平蔵の役宅に出勤すると、家中に銭箱が積まれていた。仰天した数馬は平蔵の居間に飛び込んだ。
「お頭、この銭箱は一体?」
「おお!良い所に来た。ちょうど話があったんだ。」
「いや、その前にあの金は?」
「ああ、蔵に入りきらなくてな。」
「そうじゃなくて、どうしたんですかあの金!?」
「あれは幕府から頂いた3千両を銭に両替したんだ。」
「あの窮民扶助の?何のためですか?」
「寄場資金の足しにしようと思ってな。銭の相場が上がったら売るのさ。」
数馬は絶句した。
「何ですって!?あ、あれは公金ですよ!そんな事したらお上からお咎めが。」
「落ち着け数馬!儲かれば良いんだろう?損しなけりゃお上も目を瞑るさ。」
「何を言っているんですか!もし損したら切腹ですよ!切腹!」
「ああ、そうだな。おまえもな。」
「お頭が切腹したら私たちはどうすれば良いんですか?」
「おまえも腹を切るんだから、後のことは考えなくて良いだろう?」
「ちょっと待って。さっきから何を?なぜ私が腹を切るんですか?」
「この銭の受領書な、担当者にお前の名前を書いて両替屋に渡した。」
「!?!?!?」
「だから、おまえも責任者なんだよ。」
数馬は気を失いそうだった。
「ウソでしょう!?」
「・・・・・」
「ウソでしょう!?」二度聞いた。
「そんな!ひどい!ひどすぎる!」
「まあ、慌てるな。手は打ってある。おまえも協力しろ。」
翌日、平蔵は町奉行所に江戸の主だった商人を集めた。
「其の方らに申す。諸物価が高騰して庶民が困っておるゆえ、白河様より物価抑制の要請があった。各々の申したいことがあろうが、ここはご老中の顔を立てると思って協力してほしい。」平蔵は商人たちに平身低頭して頼んだ。商人達はざわついたが、平蔵が低姿勢で臨んだことと、老中の要請とあって畏まって承った。(やる気はない)それで用件は終わったのだが、商人たちは奉行所を出た後、あちこちでヒソヒソ話を始め、やがて急いで帰っていった。
銭相場はその日のうちに急騰した。町奉行所に集められた商人たちがこぞって銭を買い始めたからである。
「よし!数馬、銭を売りに行け!」
「ははっ!」
数馬は山のような銭を大八車に載せて両替屋に飛んでいった。
「あっはっは!ちょろいもんだぜ~!」
平蔵は銭を売った利ザヤで600両の儲けを出した。
じつは内藤数馬を商人に化けさせ、町奉行所に集められた商人の中に紛れ込ませて、幕府が近々銭相場に介入すると噂を流したのだ。
「うまくいきましたな!お頭。」
「そうだな。数馬、おぬしも悪よの~!」
「フッフッフ。」数馬も悪ノリした。
(今気が付いたが何も銭の現物を持ってこさせなくても良かったな。引き換え証文を交わせば済んだのに。数馬に悪いことしたな。まあ良いか。)
訃報
寛政3年(1791)8月24日。用事から戻った内藤数馬は険しい顔で役宅に帰ってきた。
「おう数馬!ちょうど良いところに来た。お前今度は口入れ屋(人材紹介業)をやらねぇか?」
平蔵はすっかり数馬を何でも屋扱いしている。
「お頭。杉浦様がお亡くなりになりました。」
数馬は神妙な顔つきで言った。
「杉浦って、あの伊奈家の杉浦五大夫殿か?」
平蔵は真顔になった。
「そうか。惜しい人を亡くしたな。」
数馬は続けた。
「ただお亡くなりになったのではないのです。本所牢の役人から聞いたのですが、杉浦様はご当主伊奈忠尊様に処断されて監禁中に亡くなったのです。」
「何だって!?何があった?」
平蔵は驚いた。
「本所牢の役人の話では、忠尊様の不行跡を杉浦様他重臣たちが再三諫めたのにもかかわらず、全く改めることが無かったそうです。それで幕府に注進したところ忠尊様が激怒なさったとか。しかも重臣ばかりではなく古川殿含め、蟄居謹慎処分を受けた家臣が50人以上に上るとか。」
最近伊奈家の当主が仕事もせずに夜な夜な吉原や岡場所に通い詰めているという噂は平蔵も聞いていた。江戸城に登城もしていないことも。
「ううむ。これは大変な事になるな。俺が思うに伊奈家は潰れるぜ。」
「そんな。まさか?」
平蔵は杉浦のような有能な忠臣を処断すれば伊奈家は内部から瓦解する。特に関東郡代伊奈家は他家にはない専門的な能力を必要とする組織なので、熟練の人材が生命線なのだ。それを一度に何十人も処分すればすぐに機能不全になることは馬鹿でも分かる。それを伊奈忠尊はやったのである。
(伊奈家200年の栄光が、一人のくだらない人間のために潰えてしまうのか?杉浦殿、おいたわしや。ご無念お察しします。)
第5章に続く。↓
*他の章を読みたい場合は下記の章のURLをクリックしてください。
目次
第一章 本所牢屋敷-寛政元年(1789)5月6日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1789_13.html
第二章 旅路-寛政2年(1790)3月3日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_20.html
第三章 石神村-寛政2年(1790)3月4日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_73.html
第四章 石川島―寛政2年(1790)2月~寛政3年(1791)8月
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/17901791.html
第五章 馬喰町―寛政3年(1791)8月24日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1791.html
第六章 大宮宿―寛政4年(1792)3月8日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1792.html
第七章 石神村―寛政4年(1792)3月10日

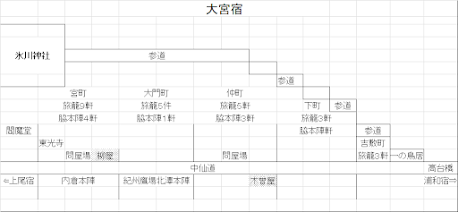
コメント
コメントを投稿