小説 お女郎縁起 第七章 石神村―寛政4年(1792)3月10日
小説 お女郎縁起
寛政秘話 石神女郎仏と大宮お女郎地蔵
改易
寛政4年(1792)3月9日。その日、衝撃の知らせが来た。村中騒然となったが、石神村どころではなく関東の民衆すべてが騒然となった。
【伊奈家改易】
つまり200年関東において民衆の守り神として崇められた関東郡代伊奈家が失脚し、お取り潰しとなったのだ。いや、正確に言えば伊奈家は親戚筋から伊奈小三郎忠盈(ただみつ)が、僅か千石の知行(ちぎょう、領地)で相続を認められたのだが、関東に絶大なる影響力を誇示した名門伊奈家は消滅したのである。
改易の直接のきっかけは、前年10月24日伊奈忠尊の正当な後継者(養子)である前当主の実子伊奈忠善(ただよし)が、忠尊派からの毒殺を恐れて出奔したことによる。忠尊はそれを隠し、幕府に対し忠善が居るように偽って報告していたのである。これを幕府は不届きとして忠尊を処断した。
「伊奈半左衛門と申せば百姓はもちろん町人に至るまで神仏のように敬い申し候処、かくの如く家断絶におよびては気の毒千万。殊に御由緒と申し候ては上もなき家筋にて惜しき事供なり」(寛政4年子年覚書)
巷間(こうかん、世間)このように惜しまれた。
翌10日、庄右衛門の家に藤田が来ていた。無論、改易の話はすでに聞き及んでいる。
「会田様から伝言があってな。」
藤田は沈んだ声で言った。
会田七左衛門は前年11月、当主伊奈忠尊の実兄、寺社奉行板倉周防守勝政によって、故杉浦五大夫の息子五郎右衛門と豊島庄七、そして永田半大夫、九郎兵衛父子とともに本所牢屋敷に収監されていたのだが、この日幕府によって無罪放免とされたのである。皮肉なことに会田等が再三訴えてきた主張は、伊奈家改易後にその正当性が認められたのである。この辺りに幕府が意図的に伊奈家の内紛を放置していたことが透けて見えるのである。
「会田様はご無事ですか?」
「ああ。今日本所牢から出所した。」
庄右衛門は絶句した。改易の詳しい内容は知らなかったので、会田がそんなことになっているとは知らなかったのである。
「大丈夫ですか?お腹を召される(切腹)ことはないですか?」
庄右衛門心配そうに言った。
「あんな奴(忠尊)のために腹を切る奴なんて居ないさ。」
家臣の忠告を聞かず、散々好き放題遊んで職務を放棄した上、忠臣達を牢に押し込めた当主など主君とは思わないのである。
詳細を語り、悔しさを滲ませる藤田を見て庄右衛門は怒りを隠せなかった。
「御上もあんまりではないですか!これだけの勲功ある伊奈様を、当主が悪いからと言ってお取り潰しにするなんて!私は御上に抗議します!」
それを聞いて藤田は背筋を伸ばして言った。
「それはやめろ。家中はバラバラになったが、中には再仕官した者も居るのだ。もし元伊奈領の領民が抗議運動などすれば、その者らが扇動したと思われ迷惑が掛かる。それに何をしたところでもう元には戻らぬ。」
「でも。」
諦めきれない庄右衛門を諭すように藤田は話した。
「そんな必要はない。だからこそ会田様の伝言を伝えに来たのだ。」
藤田は会田の伝言を話し始めた。
《赤山の百姓たちに伝えてくれ。こんなことになって済まなんだ。もうお前たちを守ってやれないが、新しい代官も鬼ではない。今まで通り堂々と仕事に精を出してくれ。どんなに厳しいことがあっても代々の御屋形様の御恩を忘れずに乗り越えて欲しい。伊奈家は武士であるが心は百姓である。わしも父も、祖父も皆そう思っていた。だからわしも越谷の実家に帰って百姓に戻る。何ら悔いはない。これからは共に励もうぞ!とな。》
「会田様。勿体なきお言葉。」(ありがとうございました。)
庄右衛門は感謝と申し訳なさを込めて心で礼を言った。
「じゃあ、俺も行くよ。」
藤田はそう言って立ち上がった。
「藤田様はこれからどうなさるので?」
藤田はにっこりと笑った。
「俺も百姓になるさ!よろしくな。名主殿。」
*伊奈家改易後、元関東郡代支配地の領民は伊奈忠尊の赦免願いを毎年出すことになる。その冒頭には以下の必ず同じ文言が付けられていた。
「恐れながら書付を以て願上げ奉り候
武州足立郡舎人領・平柳領・戸田領村々の名主・年寄・百姓代申し上げ奉り候。私ども村々の儀、御入国(家康の関東移封)以来伊奈半左衛門様の御支配を請け奉り、莫大の御憐憫を蒙り奉り、百姓相続仕り来たり、冥加至極ありがたき仕合せに存じ奉り候。」
これは自分たちが家康の関東入国(1590年)以来、伊奈半左衛門の支配を受け、莫大な憐憫をこうむって百姓を相続できたことに対する感謝の意である。
伊奈家の善政が農民の心に深く浸透していたことが分かる。しかし、これら領民の赦免願いからは改易の真相が忠尊の乱行、専横にあったことを知っていたようには見えないのである。そして幕府はこの赦免願いを一切無視したため、その後も領民は5回に渡り同じ赦免願いを繰り返すことになる。1794年に伊奈忠尊が没した後も。幕府の伊奈家に対する態度が異様に思えるのは筆者だけであろうか?
女郎尊
その日、不思議なことがあった。藤田が帰って夕刻。庄右衛門は「娘御堂」の前を通り掛かったので御堂に手を合わせた。ふと見ると扉の間に紙が差し込まれていた。
(はて?先日の娘の命日の法要の時には無かったはずだが。)
庄右衛門はその二つ折りになっている紙を開くと。
【帰命頂礼 女郎尊】と書かれていた。
「誰が!?」
周囲を見渡すが誰もいない。
(これはきっと娘を知る者が来たに違いない。それにしても女郎だって?なぜ村の誰かを訪ねない?)
庄右衛門は紙を大事にしまって持って帰った。
それから数日後。夕飯前に庄右衛門が囲炉裏で茶を沸かしていると、7歳の娘が膝の上に乗ってきた。たくさん遊んできたのか、顔は土で汚れていた。庄右衛門が手ぬぐいで拭いてやると、娘は今日あったことを話した。誰々とかくれんぼをしたとか、魚釣りをしたとか、他愛のない話をした後に、
「今日ね。“お姉さんの御堂”で遊んでいたらね。知らない男の人が御堂の前に来てね。ずっと座ってたんだよ。」
庄右衛門ははっとした。
「え?それはどんな人?いくつぐらい?」
「う~ん。喜助おじさんぐらいかな?優しそうな人。」
(喜助と同じぐらい?27、8歳ぐらいか。)
「それで、その人何していたの?」
「お姉さんの御堂にお話ししてた。あと、泣いてた。」
娘は屈託なく言った。
庄右衛門は胸がいっぱいになった。
(そうか、来てくれたのか。よかった。)
「お父さん泣いてるの?」
娘が庄右衛門を見上げて言うと、庄右衛門は涙をぬぐいながら。
「うん。ちょっとな。うれしくて。これで成仏できると思ってな。」
「成仏って?」
「死んだ人が幸せになることだよ。」
「死んだ人が?変なの。」
御堂は幾年か過ぎ、誰ともなしに女郎仏、お女郎さんと呼ばれ、いつまでも村人から大切にされたのであった。
川口市石神妙延寺「女郎仏由来」とさいたま新都心高台橋「お女郎地蔵由来」より。
了
幾(都鳥):千歳の5つ違いの妹。
高田屋儀兵衛:姉妹の実父。商人。実態は不明。安永4年3月2日死去。
利兵衛:大宮宿の飯盛旅籠(女郎宿)の主人、姉妹の育て親。
清五郎:大宮宿の材木商木曾屋の若旦那。千鳥の許嫁。千歳の2つ年上。
平太夫:木曾屋の先代。柳屋と姉妹の面倒を見てきた恩人。
小松善右衛門:大宮宿名主。
旅僧:3年前に死んだ千歳の親族を探している。
神道徳次郎:大宮宿を根城にする広域犯罪集団の頭目。
長谷川平蔵宣以(のぶため):御先手組弓頭、火付け盗賊改加役
内藤数馬:火付け盗賊改めの与力。
杉浦五大夫:関東郡代伊奈家の重臣、番頭。
会田七左衛門:関東郡代伊奈家の重臣。赤山陣屋勤務。
藤田某:伊奈家手代。赤山陣屋勤務。
岩井庄右衛門:武州足立郡石神村名主。42歳。
さと:庄右衛門の妻。
絹:庄右衛門の娘。13年前に6歳で死去。
美濃屋の女将:板橋宿の旅籠の女将。「さよ」を匿っている。ろくろの恩人。
さよ:身元不明の行き倒れ者。寛政2年3月6日石神村で死亡。
ろくろ(六郎兵衛):板橋宿問屋場雑務。元無宿人。32歳。
著者 AGC新井宿駅と地域まちづくり協議会 歴史部長 大戸昭広
*他の章を読みたい場合は下記の章のURLをクリックしてください。
目次
第一章 本所牢屋敷-寛政元年(1789)5月6日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1789_13.html
第二章 旅路-寛政2年(1790)3月3日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_20.html
第三章 石神村-寛政2年(1790)3月4日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_73.html
第四章 石川島―寛政2年(1790)2月~寛政3年(1791)8月
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/17901791.html
第五章 馬喰町―寛政3年(1791)8月24日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1791.html
第六章 大宮宿―寛政4年(1792)3月8日
https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1792.html
第七章 石神村―寛政4年(1792)3月10日

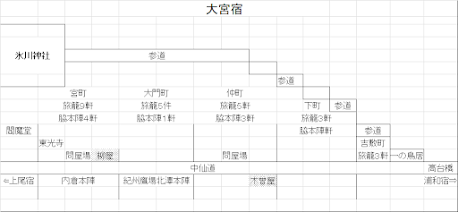
コメント
コメントを投稿